PT:27名(男性:17名、女性:10名)
OT:10名 (男性: 5名、女性:5名)
ST:4名 (男性: 1名、女性:3名)
助手:2名(男性: 1名、女性:1名)
--------------------------------------------
計43名(男性:24名、女性:19名)
※2024年5月1日時点
※男性PT1名 育児休暇中
【急性期リハビリテーション】
当院では医師の指示のもと、入院後は当日からリハビリテーションを開始しています。診療科は脳神経外科・整形外科・循環器内科・内科・心臓血管外科など多岐にわたり、
主に早期離床、機能回復、廃用症候群・二次的合併症予防に努めています。
【回復期リハビリテーション】
回復期病棟では365日リハビリテーションを行っています。急性期と同様、機能回復・日常生活動作能力向上に向けた練習に加え、入院生活中から生活の自立度を上げるように努めています。また患者さんの力を最大限活かせるような環境調整や、様々な職種と合同カンファレンスを行います。チーム一丸となって患者さんそれぞれの目標に向かってリハビリテーションを提供しています。
【外来リハビリテーション】
退院後もリハビリテーションの継続が必要と判断された患者さんに対しては、外来でのリハビリテーションを実施します。現在は整形外科疾患の方を主に行っています。機能的な回復のみではなく、生活上の問題にも着目し、より生活しやすくなるように動作指導なども行っています。
【脳神経リハビリテーションチーム】





◆心臓リハビリテーション教室・ハイキング(患者・家族対象)
当院では、心疾患を持つ患者さんを対象に包括的な教育指導を目的とした、心臓リハビリテーション教室・ハイキングを実施しています。
【教室】



 |
新入職員に向けて、各部門・チーム毎に移乗介助方法など、
臨床に必要な知識・技術の講習・実技練習を行っています。
呼吸理学療法・人工呼吸器の管理について経験豊富な理学療法士
による講習があります。

臨床で必要な触診技術は、映像で各組織を確認しながら、
技術向上を図っています。

各部門・チームで、定期的に症例報告を行い、患者さんの
利益のため討論・研鑽を行っています。

技術講習はスタッフ同士で行い、互いにフィードバック
しながらよりよい治療技術を日々求めています。
 |
日本ACLS協会認定プロバイダーの下、市民向け・科内職員
向けにBLS(一時救命処置)の講習会を実施しています。
リハビリテーション科の新入職者に対して、毎年既存のリハスタッフが必要な知識・技術を4月・5月中を目途に教育します。

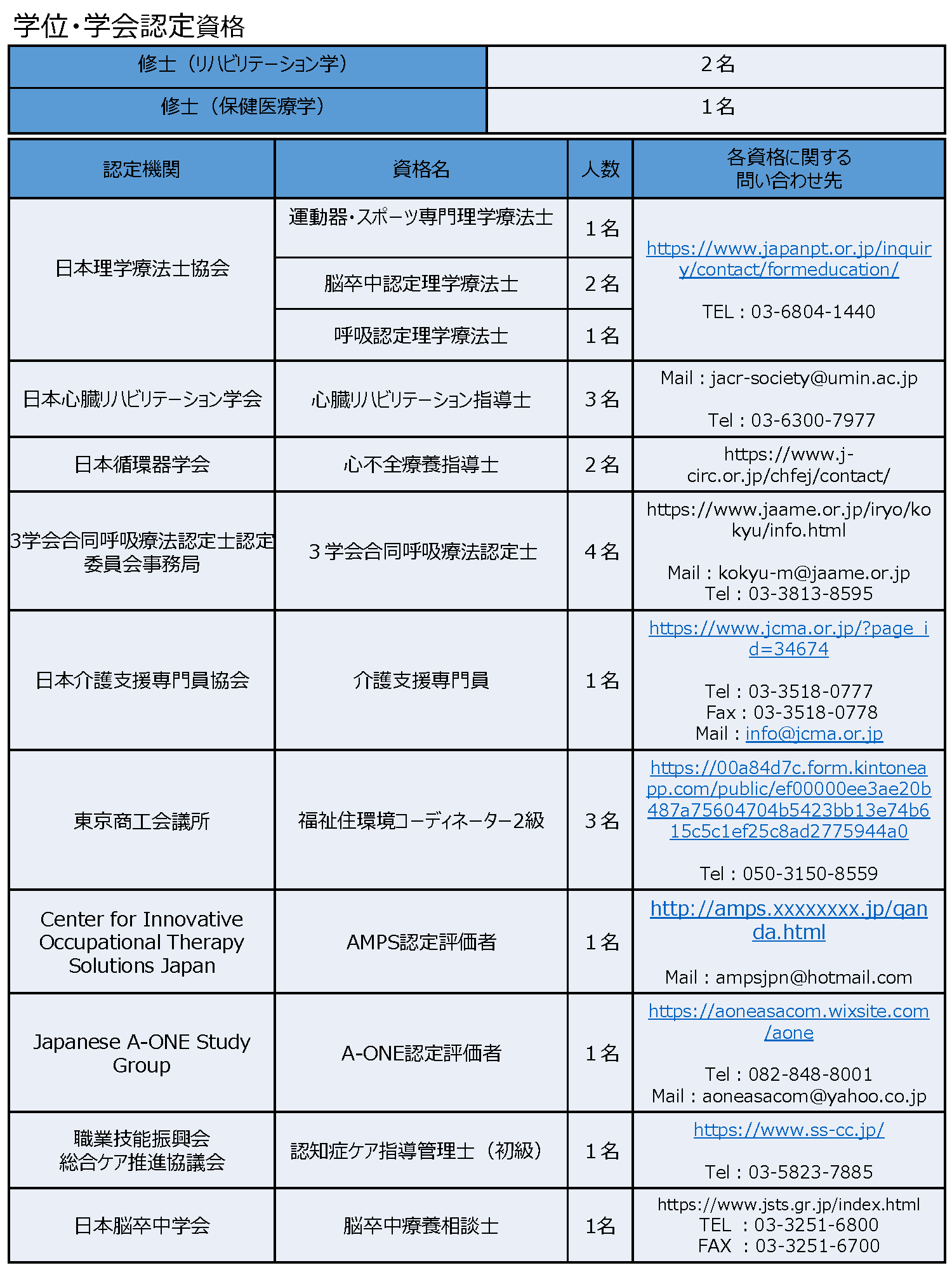

右側の廊下を進むと理学療法室と言語聴覚療法室
左側の廊下を進むと作業療法室があります。

理学療法(Physical Therary:PT)とは病気やけがなどで運動機能が低下状態の方に対して、運動機能の維持・改善を目的に運動などのリハビリを行う治療法です。理学療法室は四方を窓に囲まれた明るい訓練室です。窓を開けると爽やかな風が通り抜けます。訓練用の階段やCPX(心肺運動負荷試験)の設備も整っています。

作業療法(Occupational Therary:OT)とは病気やけがなどで 飲食、入浴、排せつ、家事動作などの日常生活を構成する作業への参加が困難となった方に対して、作業が行いやすいように訓練をする治療法のことです。作業療法は”心とからだのリハビリテーション”とも言われ、作業を通して人々の健康と安寧を促進する方法でもあります。作業療法室は優しい光に包まれた訓練室です。家事動作や入浴動作など日常生活動作の練習する 設備も整っています。

言語聴覚療法(Speech and Language Therapy)とはことばによるコミュニケーションに問題がある方に専門的な治療を実施し、自分らしい生活を構築できるよう支援する治療法です。また、摂食・嚥下の問題がある方にもリハビリを提供しています。言語聴覚療法は集中できる環境を作る必要があるため、個室で実施します。当院では通常の個室に加えて広いカーペットの部屋があり、お子さんのリハビリにも対応可能です。

理学療法室と作業療法室の外には、東京湾を一望できるリハビリパークがあります。
心地よい風と陽光を感じながら歩く練習ができ、患者さんから大人気のスポットです。
当院は3次救急指定病院であり高度急性期医療を提供する一方、回復期リハビリテーション病棟を持つ病棟でもあります。急性期から回復期におけるリハビリテーションの展開・地域への貢献等、リハビリテーション専門職の役割は多様です。三浦半島に住む地域の皆様が、リハビリテーションを通して充実した入院生活を過ごし安心して退院できるよう支援させていただきます。
リハビリテーション科は「臨床」「教育」「研究」の3つの理念をもって、患者さんや地域への貢献ができるよう努力しています。
「臨床」
地域の病院の一員として各職種と連携し、最良の医療を患者へ提供する。
思いもかけない病気や怪我により過ごす入院生活は不安なものです。我々は患者さんが安心して退院するための準備を進めるために他職種とも連携して支援をいたします。
回復期リハビリテーション病棟では病棟の看護師とも連携しリハビリテーションを提供しています。
また、日々の臨床業務のみならず「心臓リハビリテーション教室」等の患者さんへの啓蒙活動にも取り組んでいます。
「教育」
業務遂行能力・資質を共に備えた人材育成をする。
若いスタッフたちが安心して学び、多くの経験をすることができる職場づくりを進めています。
一人ひとりのスタッフが業務遂行能力のみならず資質も備えて成長し、患者さんのために専門性を発揮できるよう努めます。
そのために先輩達は若いスタッフへの支援を惜しみません。
「研究」
日々の経験・成果を自ら振り返り、今後のリハビリテーションに反映する。
日々の貴重な臨床経験をデータベースという形で蓄積し分析することを心がけています。
自ら実績を振り返ることで将来のリハビリテーションの質を高めます。
この取り組みは学術活動のみならず、「臨床」の質を高め、スタッフの「教育」にも役立っています。
リハビリテーション専門職として、多くの人々に役立つような職場づくりを目指して仕事をしています。
基本的に理学療法士は病気やケガで入院・来院された患者さんが、元の日常生活に戻るまで、様々な治療・サポートを行います。小さい子どもからお年寄りまで、すべての人を対象に、その人の身体の状態に応じて治療と予防のプログラムを作成します。当院は総合病院ですので、循環器・呼吸器、脳神経、整形、小児など様々な疾患を抱えた患者さんの理学療法を行っております。 また、心臓リハビリテーションを行った患者さんに対し、包括的支援として心臓リハビリテーション教室・ハイキングを年2回開催し、BLS講習会など患者教育にも力を入れています。
理学療法士の目標は「運動を扱うプロになる」ということです。 解剖学や生理学などの基礎的な知識はもちろんですが、運動はそれだけでは語れません。 常に知識をアップデートし、それを患者さんに還元出来るように知恵を絞り、他職種と連携を取りながら総合的に身体を見て、理学療法を行うことが運動を扱うプロとして大切だと思っています。
当院は総合病院ですので、循環器・呼吸器、脳神経、整形、小児など様々な疾患を抱えた患者さんの理学療法を行っております。 また、心臓リハビリテーションを行った患者さんに対し、包括的支援として心臓リハビリテーション教室・ハイキングを年2回開催し、BLS講習会など患者教育にも力を入れています。
当院の作業療法士は病気やケガにより、からだに障害をもった患者さんを入院初期からその人が送りたい生活に戻れるように、急性期から回復期、必要に応じては外来リハビリにて作業や活動を通して治療・サポートを行っています。小さなお子さんからお年寄りまで、様々な方にリハビリテーションを提供しています。疾患は脳血管疾患、運動器疾患、内科系疾患など多岐に渡ります。
作業療法士の目標は「その人の人生を輝かせるプロになる」ことです。病気やケガにより障害された身体機能、高次脳機能、精神機能、作業活動(セルフケア・家事・仕事など)などの改善はもちろんですが、 「その人らしさ」を取り戻すためには、意思、性格、役割、習慣、家族、趣味、仕事、生きがいなどその方を構成するすべての要素が大切だと考えます。作業療法士として「その人らしさ」を見出し、他職種と協力しながら生活をもう一度輝かせていきたいと思っています。
当院の特徴としてケアミックス型の総合病院であるため、様々な病態・病期の方に作業療法を提供することが出来ます。また定期的に急性期チームと回復期チームのメンバーを入れ替えて、常に幅広い経験を得られるようにしています。 また月2回の勉強会を行い、基礎知識や臨床スキルを磨くことが出来ます。1~3年目までの新人教育体制はもちろん、4年目以降であっても自分のキャリアデザインを叶えられるようなサポート体制づくりをしています。 うわまち病院のOT部門のモットーは、患者さんの「またやりたい」を「また出来る」にすることです。この理念をもって、日々臨床、教育、自己研鑽に励んでいます。
当院の言語聴覚士が関わる領域は、言語聴覚領域全般となっており、成人分野から小児分野まで多岐にわたります。実際に、領域はとても広いですが、養成校ではすべて言語聴覚士の職務だと学んだ分野です。失語症、高次脳機能障害、構音障害、音声障害、嚥下障害、吃音、小児言語発達障害(言語発達遅滞、自閉症、学習障害など)、発達障害に伴う嚥下障害、機能性・器質性構音障害、耳鼻咽喉科領域全般(聴力検査含む)、聴覚障害、補聴器の選定・調整・・・などこのように羅列すると大変に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、職員皆、全ての領域にやりがいをもって臨んでいます。初めから、何でも関わることができる人などはいません。先輩療法士の指導を受けながら、少しずつその分野の楽しさを実感できるまでに成長しています。また、当院では急性期の患者さんから回復期を経て次のステップへ至るまで、一人の患者さんの回復経過を共に歩むことができます。
言語聴覚士の目標は、「コミュニケーションを扱うプロになる」ということです。 日頃接する患者さんは皆、何らかのコミュニケーション障害を持ち合わせている方々です。言いたいことが言えない。思いをうまく伝えられない。言葉の意味が理解できない。社会で生活していく中でコミュニケーション障害というものはとても負担になることです。患者さんと。ご家族と。医師と。他のコメディカルスタッフと。誰とでも、良いコミュニケーションを取り、コミュニケーションをとることが難しい方々の代弁者となれるのが言語聴覚士であると考えます。
言語聴覚領域全般といわれると、自分にはできるか、ついていけるか、不安になってしまうかもしれませんが、問題ありません。先輩言語聴覚士が、それぞれ丁寧に指導を行います。また、興味のある分野に重点を置いて学ぶことも可能です。特に興味のある分野がなくても、たくさんの分野の経験ができるため、自分に向いている領域や好きな分野を見つけることができます。たくさんの経験ができることが当院の言語聴覚部門の強みです。